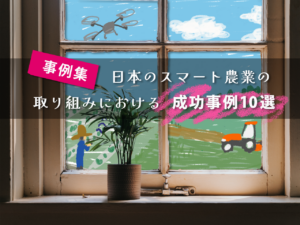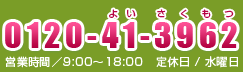相続財産の中に、あるいは相続しそうな財産として農地や農業用地、農機具がある場合にはどう対処したらいいのでしょうか。農業にかかわってこなかった人は、その手続きの煩雑さに驚いてしまうかもしれません。
単なる不動産や動産の相続とは違い、農業関連は独自の手続きが必要です。農地・農業相続のメリット・デメリットから注意点、納税猶予制度、相続の具体的な方法までを詳しく説明します。
▼ ▼ ▼
農機具ランドあぐり家はプロの査定スタッフが常駐しており、スピーディーに適正な査定金額をご提示します。出張査定無料!古い・動かない農機具でも買取可能です。

農地を相続したらどうしたらいいのか
相続財産の中に農地や農機具など農業関連のものがあったときにするべきことをまとめて解説します。
まずは相続するものの中に土地が含まれている場合は、それが農地かどうか、また農地の種類の確認が必要です。
農地には5つの種類があり、農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地、第2種農地、第3種農地に分けられます。この種類によって、できる手続きが変わってくるので、まず調べましょう。
農業を行う場合
相続する土地が農地に分類されていて、そのまま相続して農業を行う場合、不動産の名義変更(所有権移転登記)と農業委員会からの許可が必要です。
農地はすべて農業委員会が管掌しています。売買や贈与によって農地を得た場合は別途農地法の許可が必要ですが、相続の場合は不要です。農業委員会に規定の書類を窓口で届け出るだけで問題ありません。
また、納税猶予の特例制度があるのでその申請が可能かの確認を行い、可能であれば申請していきます。
農機具も相続財産に含まれていたら、大型のトラクターやコンバイン、軽トラなどがないか確認しましょう。それら大型の農機具は、ナンバープレートが付いている場合があります。付いていれば名義変更が必要です。
農業をすでに行っているのであれば農地などの名義変更はスムーズですが、これからの場合は農業を開始するための手続きも並行して行う必要があるでしょう。
農業を行わない場合
農業を行う予定はないのに農地などを相続する場合、以下の方法が取れます。
・「相続土地国庫帰属法」を利用して農地を放棄する
・ほかの相続人と話し合って農地以外を分割してもらう
・農地転用を行って宅地として取り扱う
先述のように、農地はすべて農業委員会が管理していて、しかも農業をしない人が農地を農地として所有することはできません。
そのため、農業をしない場合は、農地ではなくするために宅地に転用してしまうか、農地をそもそも所有しないように権利の放棄をするか、農地の価値の分を別のものに変えてもらって相続するしかありません。
農業を行わないと決めているのであれば、はじめから上記の対応を取っておくと手続きが楽になると言ってよいでしょう。
詳しくは
農地を相続!農業をしたくないときに取るべき行動とポイントを解説
農業・農地を相続するメリット・デメリット
農業・農地を相続するかどうかは大きな選択になります。自分がどうするべきか考えるために、メリット・デメリットを整理して考えるのがおすすめです。
相続のメリット
相続すると、これまでの農業の経歴をうまく活用して収入源とできる可能性があります。さらに、宅地に転用できる種類の農地であったなら、そこに住宅を建てられるかもしれません。
一方で、農地のままにしておくと固定資産税が低くなったり、相続税の納税猶予があったりと、税金面での特徴もあります。いますぐに農業を始められないという事情があっても、農地を所有する負担は軽くなると言えます。
メリットをまとめると以下の通りです。
・農業収入や農地の貸出により利益を得られる
・農地転用できる農地なら宅地化やその他の活用も
・固定資産税が低い
・相続税の納税猶予がある
相続のデメリット
反対に、相続をするデメリットもいくつかあります。まずは、相続の手続き自体が初心者には大変なことです。不慣れな書類手続きを、一定の期間内に行わなくてはなりません。専門家に依頼することもできますが、知らなくてはならないことが増えるのに変わりありません。
また、農地やその他設備の維持や管理には手間も時間もかかります。放置しておくと雑草が生えたり、設備に異常が出てきたりと、何かとするべきことが増えてくるものです。
それだけではなく、農業は手放しに始めて成功できるというものでもありません。育てる作物や土壌についての知識を深め、販売までを考えた計画を立てる必要があります。知識のないまま始めてしまうと、発育不良や害虫被害などで損害が出るかもしれません。
デメリットをまとめると以下の通りです。
・相続の手続き自体に手間がかかる
・農地や設備の維持管理にもコストがかかる
・知識がなく突然始めると農業を失敗するリスクがある
納税猶予とは?
納税猶予制度とは、「農業を営んでいた被相続人または特定貸付け等を行っていた被相続人から一定の相続人が一定の農地等を相続や遺贈によって取得し、農業を営む場合または特定貸付け等を行う場合には、一定の要件の下にその取得した農地等の価額のうち農業投資価格による価額を超える部分に対応する相続税額は、その納税が猶予される」という制度です。
この農地等納税猶予税額は、特例の適用を受けた農業相続人が死亡した場合等に免除されます。
被相続人と相続人、農地のそれぞれについて要件が定められているので、簡単に解説します。
被相続人の要件
被相続人は、以下のいずれかに該当している必要があります。
・死亡日まで農業を営んでいたこと
・生前に、後継者に農地を一括贈与していたこと
・死亡日まで納税猶予を受けていた農業相続人あるいは受贈者で、営農困難時に農地を貸付けしていたこと
・死亡日まで特定貸付を行っていたこと
相続人の要件
相続人は、以下のいずれかに該当している必要があります。
・相続税申告期限までに農業経営を開始し、その後も継続して農業を行うと認められること
・相続税申告期限までに、相続した農地を特定貸付していること
・被相続人から生前一括贈与を受けた農地について、納税猶予が適用されていること
農地の要件
相続される農地の条件として、以下のいずれかに該当している必要があります。
・相続税申告期限までに遺産分割の協議が成立していること
・被相続人の生前一括贈与において、贈与税の特例が適用されていること
・相続開始の年に、被相続人から一括贈与されていること
これらの要件を満たせば、農業投資価格を超える部分の農地にかかる相続税が猶予されます。農業を継続することで、最終的に猶予された相続税が免除される仕組みです。
注意点
注意が必要なのは、農業をやめるときや農地を誰かに譲ったとき、免除された相続税を納税しなくてはならない点です。あくまで当事者が農業をしているときに適用されるということを覚えておきましょう。なお、「特定貸付け」に該当する場合も免除されます。
農地を相続するための手続き方法
農地を相続するためにするべき手続きについて概要を解説します。
① 法務局で登記する
不動産の登記に関しては、速やかに法務局で登記を行うことが望ましいとされています。相続する農地の所有者の変更を届け出るために、以下の書類を記入し提出します。
・所有権移転登記申請書
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
・相続人の住民票または戸籍の附票
・遺言書または遺産分割協議書
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明(遺産分割協議書を提出する場合)
・固定資産評価証明書
② 農業委員会に相続の旨を届け出る
法務局に対して、相続による登記の変更を申請し完了したら、次は速やかに農業委員会へ届け出を行います。農業委員会は各自治体に接地されているので、所在地や連絡先を確認して訪れましょう。
農業委員会に提出する書類は以下の通りです。
・農地の登記事項証明書
・農地法第3条の3第1項の規定による届出書
農業や農地の相続が発生したら、財産の処分はあぐり家におまかせ
農業をこれから始める場合、農機具を新たに購入する機会もあるでしょう。相続で引き継いだ農業であっても、使い古した農機具だと早々に買い替えが必要になるかもしれません。
事業を始めたてで費用を抑えるなら、中古での農機具購入がおすすめです。新品での購入よりも、半分以下の価格で購入できる場合があります。最新の機能やこだわりの機能がなければ、まず中古市場を確認してみるのはいかがでしょうか。あぐり家でも多くの中古農機具を販売しているので、チェックしてみてください。
一方で、相続財産のなかに農機具が入っている場合は、その処分に迷うことと思います。その場合は専門の買取業者に買取を依頼するのがおすすめで、手間なく高い金額で売れることが期待できます。
あぐり家は、農機具の修理の知識が豊富で多くの農機具を売買している農機具専門の買取・販売業者です。古くて壊れているような農機具でも、無料で買取査定を行っています。まずは査定の依頼をしてみてください。
▶農機具のリサイクル方法について詳しく知りたい方はこちら
使わない農機具は処分?リサイクル?実は買取依頼をするとオトクな理由
▶農機具の処分方法について詳しく知りたい方はこちら
【使わなくなった農機具を売りたい方へ】買取価格の相場は?高価買取のポイント解説